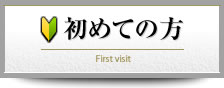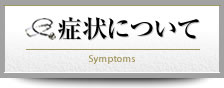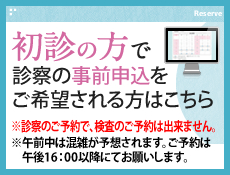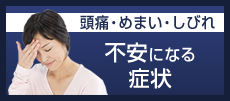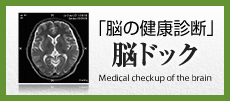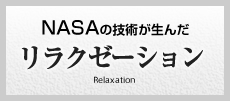当院では、希望者の方はもちろん生活習慣病(高血圧症、糖尿病、高脂血症の中で)を二つ以上お持ちの方に対して頸動脈エコー検査をおすすめしています。その結果、かなりの方に異常所見がある事がわかっています。最も多い異常所見はもちろんプラーク形成等の動脈硬化性病変ですが、脳外科医の私にとって意外だったのは、思いの他甲状腺腫瘍を持っておられる方が多いという事です。その数は被検者方の方の半分以上になります。また数%(5名)の方は悪性腫瘍(癌)で他施設で手術をして頂きました。この事はまさにひょうたんから駒で、非常に驚いています。今後、積極的にこの検査を皆様におすすめしようと思っています。
開業して13年が経過し、医師になり早32年の年月が流れました。その間におそらく数万人以上の患者さんを診察し現在に至っています。診察室での患者さんに対する心構えについて、診療生活で特に影響を受け、目標とさせて頂いた先輩方が数名おられます。その方々に心からお礼をする気持ちを込めて、今の心境を語りたいと思います。
診察室では常に患者さんを自分の親や肉親と思い診察にあたっています。これは綺麗事ではなく、現在進行形で、私の2歳半になる娘の健康診断、予防接種、風邪などで受診の際に色々な先生にお世話になり、益々この気持ちが強くなりました。子供の事なので夜間救急に行き、沢山の患者さんがいるにも関わらず、本当に時間をかけ納得いくまで説明してくれる先生。予防接種の際に、おまり質問を聞いてくれないオーラが出ている先生、先生に質問をしている私の背中を診察室から処置室へ押したナースとそれが日常的と黙認する先生等、様々の医療機関があります。本当に尊敬できる人、全く出来ない人等様々ですが、ある大教授の言われた、医師自ら律する気持ちが必要です。何故なら、医師の70%は変人だからと。
今自分の診察室での姿勢は、出来るだけ多くの時間をさいて患者さんのお話を聞く、もちろん井戸端会議ではなくお友達でもありませんので、長い話を適切な方向へ端的に切り上げる様に、しかも患者さんに満足して頂ける診察をめざしています。また外国の方には拙い英語での説明や漢字や文字でお知らせしたり、また耳のご不自由な方はよく聞こえる側でお話をする様にー具体的には診察室で診察用の椅子と患者さんの椅子を変わって頂き、よく聞こえる側に座り直して説明するようにしています。
何時も自分が患者さんになったらと思い診察をする今日この頃です。
HPの患者さんの声の欄に新しい記事を掲載しました。大変ありがとうございます。皆様が当院を受診される際の御参考になれば幸いと思います。
クリニックで高血圧症の勉強会を行いました。当日は参加者は多くありませんでしたが、会の後半で日頃皆様が疑問に思われている事に対して御説明できる機会を持つ事が出来、充実した会になりました。以下勉強会の内容を①管理栄養士②薬剤師③医師の順番で記載します。
管理栄養士の説明のポイント
高血圧の食事療法のポイントは大きく分けて、①~③の3つのポイントがあります。
①適正体重の維持とエネルギーコントロール
●適正体重(kg)=身長(m)×身長(m)×22
現在の体重と比較して、太りすぎの場合はエネルギーコントロールが必要です。
例)身長が160cmの方の適正体重は1.6X1.6X22=56.3kg
●1日の適正エネルギー(kcal)=標準体重1)×身体活動量2)
1)標準体重=身長(m)×身長(m)×22
2)軽労働:25~30,中労働:30~35,重労働:30以上
例)56kgの人で軽作業25の人は56X25=1400kcal
②1日6g未満を目標に減塩(Step1~Step4)
●Step1:引き算感覚でまず“減塩”
食品の塩分量を知り、食塩を多く含むものを減らしたり除くことからはじめましょう。
※食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)×2.54÷1,000
例)食品の栄養成分表示を見て100gあたりナトリウムが168mgとすると
食塩相当量は168×2.54÷1,000=0.4gになります。
●Step2:料理を工夫して“減塩”
・鮮度のよい食品や旬のものを用いて、素材そのものの味を楽しむ
・食材・調理法で薄味をカバー
・調味料は計量して使う
・素材の中に味をしみ込ませるよりも素材の表面に適度な味が付いている料理
・市販食品、加工食品の使いすぎは避ける
●Step3:汁物で“減塩”
一般的に、みそ汁を「飲む」から具を多くして「食べる」に意識を変えてみましょう。
●Step4:味にメリハリをつけてストレス軽減
1品だけを“少量”好みの味のものを添えたり、主菜にはしっかりした味付けをして副菜は少し塩分を控えるようにするなど一食の中でも味にメリハリをつけ、単調な味付けにならないように工夫しましょう。レモンの酸味を利用して減塩してみても良いでしょう。
③カリウムを十分にとる
野菜や果物、いも類、海藻類に含まれているカリウムは、ナトリウムを体外に排泄して、血圧の上昇を防ぐ働きがあるため、献立に取り入れてバランスのよい食事にしましょう。
薬剤師の説明のポイント
高血圧の薬物治療について
①高血圧を放置することで、「動脈硬化」が進み「心臓病(狭心症、心筋梗塞)、脳卒中」を発症する確率が高まり、死に至ることもあるので、「血圧が高い」と言われたら治療を開始しましょう。高齢者の高血圧症で薬を服用している場合、服用しない場合に比べて、脳卒中の死亡率が36%減少し、心筋梗塞や狭心症の死亡率が25%減少した報告があります。更に高血圧症の治療で「認知症」も予防できることがわかっています。
②血圧は、年齢や疾患(糖尿病、慢性腎臓病など)によって降圧目標の値が変わってきますので、適正な血圧を知って治療を行いましょう。
③薬で治療をされていても降圧目標を達成できている方は約3割との報告があり、1種類で目標値に達成できない場合は、2種類以上の薬を飲む場合があります。最近では、合剤(ごうざい)と呼ばれる2種類の成分が1錠になった薬が多く発売されるようになり、治療効果が高まっています。
④最後に、「お薬を頼もしい味方と考え、前向きに続けていきましょう」、「血圧が下がっても自己判断で勝手に薬を止めたり、減らしたりしないようにしましょう」の2点をお伝えしました。
医師の説明のポイント
①高血圧症とは血圧が高い状態が続いてしまう病気です。目だった症状はありませんが、高い血圧が続くと脳血管や心臓にダメージを与えます。
②高血圧症の原因の90%以上は生活習慣や遺伝が関係しています。塩分の取りすぎや過労、ストレスでも血圧を上昇させます。
③適正は血圧の値を知る事や自宅での血圧測定の方法をマスターしましょう。また季節で血圧の変化する事や肥満解消で血圧が改善する事も知りましょう。