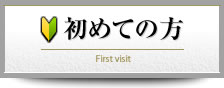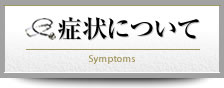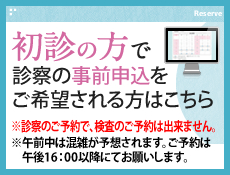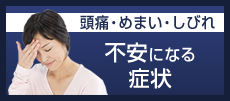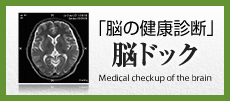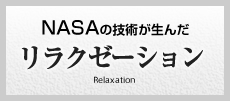頭部外傷の場合、最初の24時間の観察が大切で、特に急性頭蓋内出血の発症の場合には、外傷直後から4~5時間の間に意識状態に変化をきたします。頭皮下血腫を合併する場合は勿論の事、外観が問題ない場合でも、生命に重大な影響を及ぼす事がありますので、外傷の後で心配な場合は脳神経外科専門医の診察を受ける事をお勧めいたします。頭部外傷は一般的には、転倒しやすい1歳から3歳までの幼児と高齢者に多い特徴が有ります。幼児では3歳まで頭と躯幹とのアンバランスがあり転びやすい様です。頭部外傷後に経過を見る場合には、次の様な事項に注意しましょう。①意識状態はどうか?幼児の場合は不機嫌ではないか?②頭痛はないか?③吐き気や嘔吐はないか?④手足のしびれ感や麻痺はないか?等です。また、当日は出来るだけ安静にして、お風呂へ入る事を控えましょう。脳圧が上昇して吐き気をもよおす事があります。また、アルコールや刺激の強い食べ物も控えましょう。最後に、50歳以上の男性でお酒をたしなまれる方に多い様ですが、外傷後3週間~2ヶ月程度の間に徐々に進む、認知症、運動麻痺、尿失禁が出現した場合は、慢性硬膜下血腫の発症を疑って再度受診して下さい。漢方薬や手術で上記の症状は回復します。一般的に治る認知症と言われています。なお、著者の経験では35歳の女性で、頭部打撲1ヶ月後に慢性硬膜下血腫を発症された方がいますので、50歳以下は大丈夫と言う訳ではないようです。
塩分摂取量の多い日本人は三人に一人が高血圧症で、諸外国よりその割合がきわめて高い様です。またある統計では、高血圧症の改善率は3割でそれ以外の7割の患者さんは降圧剤を飲んでいても、収縮期の血圧が140以上か拡張期の血圧が90以上で治療の効果が不十分という結果が出ています。当院の院長は脳神経外科医で、若い頃から高血圧症の治療経験が豊富で充分な知識を持ち合わせています。高血圧症の患者さんで血圧の改善が不十分な方、血圧の変動が強い方は当院へ御相談下さい。
以前にも書きましたが、交通事故は誰にとってもいやなものです。特に、事故後の体調の管理やその他保険会社等との話し合いは、自賠責保険等の知識や情報が少ない上に、相手方の保険会社の方はプロなので結果損をする事も多い可能性があります。その事が益々体調を崩す原因にもなります。当院の院長は、三井住友海上の顧問医ですので、事故後の体調の事やトラブルの解消の御相談に乗らせて頂きます。お気軽に御相談下さい。今日来院された患者さんも、検査結果と相手方の自賠責保険の請求方法や容認されている治療期間をご説明して安心して帰られました。
来院された患者さんで手術が必要となった方に最良の治療を受けて頂くため、当院では院長自身ネットワークや臨床及び手術経験からその病気に最適なドクターに治療をお願いしています。大部分の患者さんは、広島市内の有名な脳神経外科のドクターに治療をお願いしていますが、中には以下の理由で過去に京都大学やその関連病院のドクター、京都大学以外の有名なドクターに治療をお願いしたケースがあります。
①病気が特殊で市内で治療が困難な方②患者さんの強いご希望③お子様が遠方におられ、お子様の近くの名医に治療を希望された。
等がその理由となります。患者さん個人個人で様々なお考えがあります。この様な場合はどうぞ遠慮なくご相談下さい。