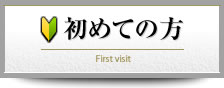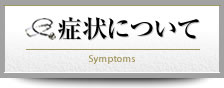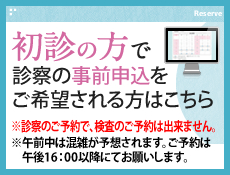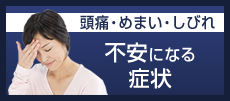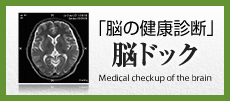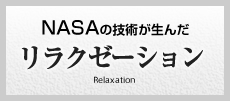生活習慣病の予防や治療は食事療法と運動療法が基本です。これらの治療を充分に行っても、血液検査や血圧の値が不良の場合には薬物療法になります。
運動療法については、決められた方法は有りませんが、最低限度推奨される運動量が解明されはじめています。具体的には、有酸素運動としてしっかりと1日6000歩以上歩く事です。この根拠は、長野県と香川県の人の歩数と生活習慣病(糖尿病等)の罹患率の統計から、長野県の人は平均で6000歩以上歩き有病率が低く、逆に香川県の人では6000歩未満で有病率が高い事がわかりました。
この6000歩をわかりやすく説明すると、歩幅が60~65cmと考え3.6~3.9kmの距離、時間にして40分程度(時速5km)になります。生活習慣病の予防は平素の食事や運動が大切ですので、どうか参考にして下さい。
頚動脈に対しての超音波検査(以下エコー検査)で評価をする事は、頚動脈の状態は知り、更に現在の頚動脈を含めた全身の動脈硬化の状態を評価するという意味があります。具体的には、頚動脈が先天的に細い場合や、動脈硬化で細くなっていたり、部分的に動脈壁が厚くなった状態を経時的に非侵襲的(痛みがなく)に検査が可能です。
この動脈硬化の指標として、動脈壁の中膜と内膜の複合体(通称IMT)を測定し、その厚みで病態を評価しています。通常20歳代ではその厚みが0.3mmで10歳年をとる毎に0.1mm増加します。つまり、正常で1mmに達する年齢は90歳という事になります。従って、60歳でIMTが1mm以上ある方は、動脈硬化があると判断します。
更にIMTが1mm以上の場合をプラークと呼んでいます。
最近の治験で、高脂血症の治療薬であるスタチン製剤がこのIMTの肥厚を改善すると言う報告があり注目されています。(検査についての頁を参照してください)
めまいの原因は①椎骨脳底動脈循環不全症又は②発作性頭位めまい症であるが場合が圧倒的に多い様です。一方、「めまいと言えばメニエール」とよく言われているメニエール病は、一般受診の患者さんの中での頻度は0.6%程度です(中山2005)。従って、めまいの原因がメニエール病である可能性は、極めて低い事になります。また、耳の病気が原因のめまいの場合は、突然の耳鳴りや難聴の症状も同時に起こる事が普通です。
上記①場合は、高齢者の方や、ペースメーカーを装着しておられる方がめまいを起こした場合は、まず第一に考えてよい疾患です。この椎骨脳底動脈循環不全症は、体のバランスをとっている脳神経に直接栄養を送っている血管の動脈硬化によりめまいが起こります。この為、将来脳卒中を起こす可能性があり、頭部MRI及びMRA検査は必要と考えます。 また②の発作性頭位めまい症は、美容院等で頭を洗う時や洗濯物を物干しに干す際に起こるめまいの事です。耳石の位置の移動により起こると考えられています。しかし、この様なめまいの場合でも、脳腫瘍が隠れている可能性も否定できません。この為、頭部の精密検査を行い生命に関わるような重大な病気がない事を確定する事が必要です。
以上から、めまいがあり、耳鳴りや難聴等の他の耳の症状を伴わない時には、まずは頭の精密検査が必要です。
薬は、日々進歩しています。当たり前のことですが、新しい薬ほど効果があり副作用が少ないものです。しかし、現状では、薬に対する根強い不信感があり、長期の連用に対する抵抗感がある事も事実です。例えば、安定剤や睡眠導入剤を長期に連用すると、頭が呆けるという迷信がまかり通っています。この事は大変な誤解であり、正しい薬を正しい用法で服用すると決して呆ける事はありません。
この様な誤解をまねく一つの要因として、薬害肝炎や薬害エイズの問題で明らかになった様に、過去の厚生労働省の薬物に関する審査に諸問題があった事は事実です。この為、国民の多くの方は、薬に関しての抵抗感があり、さらにその長期の服用には簡単には解決できない不信感があるようです。また新しい薬に対する厚生労働省の許可をする時期も世界水準から見ると、先進国では圧倒的に遅く、驚く事に世界でも100番目(100ヶ国)以下の順位となることが今や常識になっています。このこと自体、国民にとっては大変な不幸です。何故なら日本で開発された世界に誇れる良薬や、諸外国の優秀な薬(販売前に何度も試験をして安全性の確立した)を発売したあと直ぐに日本では手に入れる事が出来ません。
具体例を挙げると、代表的な認知症のアルツハイマー病の治療薬ですが、日本ではいまだにアリセプト錠しか厚生労働省から認可がおりてないのが現状です。しかし、日本はご存知の様に今や世界一の高齢化社会で、65歳以上の方の13人に一人が認知症と言われています。アリセプト錠も良い薬ですが、諸外国ではそれ以外にも良い薬が認可、実用化され効果を発揮しています。医師会や薬剤師会も、もっと声を大にして状況をお知らせしたいのですが、さまざまな箇所に遠慮がある様です。
今後我々医師が色々な場所で薬の現状について、正確な情報を提供し、少しでも薬に対する抵抗感をなくしていく努力が必要と考えます。