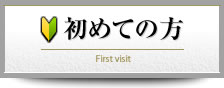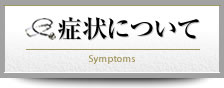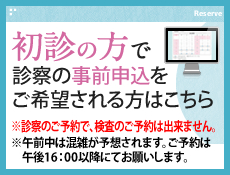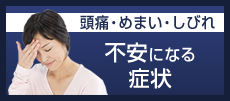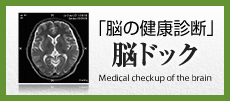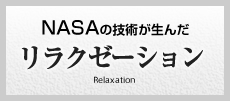急性硬膜下血腫は、一般的には頭部外傷直後から数時間以内に発症します。しかし外傷がなく、原因が不明のいわゆる急性特発性硬膜下血腫の病態がある事も知られています。例えばMizushima(Neurol Med Chir, 99)らは外傷、脳の表面の皮質動静脈奇形、血管腫、動脈瘤、また患者さんの出血傾向と関係ない急性特発性硬膜下血腫の症例が54例あったと報告しています。石井(脳神経外科,04)らはこの病態の症例報告の結語として脳梗塞、心筋梗塞等の動脈硬化性病変が基礎疾患にあり、それに加えて易出血性を助長する薬剤が投与されていた事が血腫発生に影響を与えるとしています。また、他の報告では出血性素因の一つとして血友病の患者さんにおける急性硬膜下血腫の症例でBalak(Surgical Neurology, 97)らは、成人発症の急性硬膜下血腫の半数例が外傷との因果関係はなかったと報告しています。
以上稀な病態ですが、御紹介します。
頭部外傷による高次機能障害(認知症)
頭部外傷が原因で高次機能障害を引き起こす為には次の3要素が一般的には必要です。
(ア)頭部外傷によって、脳に対する強い外力が加わり、その結果、画像で脳の萎縮や脳室の拡大が認められること。
(イ)意識障害が一定期間持続すること。
(ウ)外傷後の人格の変化、知能低下が顕著なこと。
仮に、上記(ア)を欠いている様な受傷直後の頭部CTやMRIが異常なく、後に高次機能障害を引き起こす様な状態とは、やや特殊な例として画像所見では一見正常と思われるび漫性軸索損傷の状態があります。このび漫性軸索損傷とは、直接に外力が頭部に加わる脳挫傷と違い、間接的な外力が特に回転加速度的に加わる事で、脳全体特に脳深部の神経組織(軸索や血管)にいわゆる歪みが生じる事が外傷機転と考えられています。このため、例え画像所見で異常がない状態【軸索(脳神経細胞同士の連絡網)の異常は画像所見では描出が不可能の為】でも、頭蓋内は深部を中心としてダメージが強く、このため意識障害等の脳全般の臨床症状が起こります。
このびまん性軸索損傷で、臨床例をあげるなら、最軽症型が脳振盪であり、最重症型が外傷後植物状態です。また、日常診療で見かける脳振盪(一般的には数秒から数分の意識障害)の症例が後に高次機能障害を引き起こした症例の経験は私にはありません。
従って高次機能障害を引き起こす程の頭部外傷の場合は、受傷時には脳振盪よりもより重症な意識障害が不可欠と考えます。
妊娠中の抗痙攣剤の服用はこれらの薬の催奇形性から十分に事前の検討が必要です。一般的に全身痙攣等の発作の為に妊娠中や出産中に、胎児や母体に危険を引きこす可能性が抗痙攣剤の催奇形性を上まれば服用が許される事になります。具体的に考えれば正常な出産に際しての奇形の頻度は2~3%と考えられ、抗痙攣剤の種類によって異なりますが、最も安全とされる抗痙攣剤を服用してもこの頻度は2倍から3倍に増加するようです。従って妊娠中に抗痙攣剤を服用する事での奇形の頻度は4%~9%となります。つまり約1/11~1/25の出産で問題となる事になります。
一方、抗痙攣剤服用中でも痙攣発作(発作の重症度に関係なく)が1回以上/年起こる可能性のある症例では、薬を服用する事プラス発作の危険性の2重の問題から医師による妊娠許可の可能性は難しい事になります。
従ってより厳しく基準で症例を限定すると、癲癇の患者さんで痙攣発作のコントロールが3~5年間以上出来ており、なおかつ脳波が正常な症例で上記の内容を十分に理解された御夫婦に限り妊娠が許されると考えます。