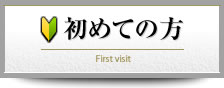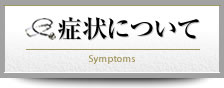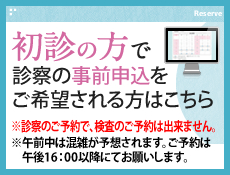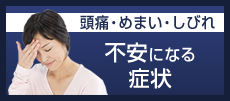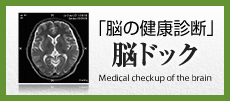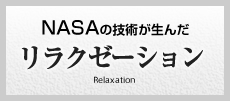脳卒中の予防には、その原因つまり危険因子を良く知り、生活習慣を改善する事が重要です。それ為には、危険因子への正確な知識を持つ事が大切です。
この危険因子には、予防可能なものとそうでないものがあります。予防不可能な危険因子を具体的に挙げると年齢、性別、遺伝的素因があります。例えば、脳梗塞では80歳代の方は60歳代の方より3倍の罹患率があると考えられています。また男性は、女性よりも脳梗塞罹患率が高い事が知られています。更に父親が脳梗塞の場合は約8倍、母親が脳梗塞の場合は約3倍、脳梗塞に罹患しやすいとする報告もあります。これらはあらかじめ予防が不可能ですが、正確な知識を持つ事が大切な事と考えます。その一方で、生活習慣を変えたり、薬を服用したり、運動や食事療法で予防が可能な危険因子もあります。具体的には、高血圧症、糖尿病、高脂血症、喫煙、過度の飲酒、高尿酸血症、心臓疾患の合併等があげられます。上記の生活習慣病(高血圧症、糖尿病、高脂血症、高尿酸血症、心疾患)にそれぞれ単独あるいは複数に罹患すると脳卒中の罹患率が数倍から数十倍になります。また喫煙に関してはタバコ1本/日から危険率が上昇しますので禁煙が必要です。飲酒に関しては、1日にビール1本、又は日本酒1合程度で止めておきましょう。運動療法に関しては、激しい運動をする必要はなく自分の体力に合わせて歩く事をお勧めします。具体的には1日6000歩(2~3km)程度が理想の様です。今からの季節は室内と室外との温度差があり、長時間外出される場合は厚着をしてまた、特に寒い日のゴルフやテニスは控える様にしましょう。
最後に、40歳以上方は少なくとも年に1回程度検診を受けられ、自分の健康状態をよく知る事が重要です。もし上記の危険因子に心あたりのある方は一度脳のMRI検査を受けられる事をお勧め致します。MRI検査を行う事で、無症状であっても脳梗塞(かくれ脳梗塞又は無症候性脳梗塞)が見つかる事や、破裂してクモ膜下出血を起こす前の状態の血管の瘤(未破裂脳動脈瘤)が見つかる事もあります。その場合は専門医(脳神経外科、神経内科)の治療が必要になります。
脳梗塞は脳の動脈が閉塞して脳細胞が虚血(乏血)状態に陥り回復出来なくなった状態を言います。この脳梗塞には2種類あり脳の太い動脈(主幹動脈の第 3~4分枝まで=長径1mm前後以上の太さの血管)が閉塞して起こる狭義の脳梗塞と穿通枝動脈(長径200~300Å=0.2~0.3mmの太さの血管)が閉塞して起こるラクナ梗塞(梗塞の長径25mm以下のもの)に大別されます。ラクナ梗塞は別名孔梗塞と呼ばれています。この孔の意味は突き抜けた孔と言う意味ですから脳実質内に突き抜けた状態で存在している梗塞の事です。ラクナ梗塞は最近まで日本人に多く、狭義の脳梗塞は欧米人に多いとされてきましたが、日本人の食生活の変化(洋食化)によりラクナ梗塞対脳梗塞の比率も欧米に近づいています。事実かつて平均寿命が全国ナンバーワンであった沖縄県の男性の平均寿命が第17位に転落した統計結果も無関係ではない様です。
脳梗塞の主な原因は予防できない危険因子としは家族歴(第3親等内の身内に脳卒中がないか)、性別、年齢があり、予防可能な危険因子として、高血圧症、糖尿病、高脂血症、高尿酸血症、喫煙、飲酒、心疾患の合併等があげられます。
一般的に加齢のみでも大脳深部(白質)にラクナ梗塞が出現し、早い人では40歳代から無症候性脳梗塞(手足の麻痺等のない脳梗塞)を認めます。従って患者さんの年齢、ラクナ梗塞の数と大きさと存在場所によって加齢変化か病的な変化かを鑑別する事は日常診療で重要です。
当院ではラクナ梗塞の大きさが10mm以上でラクナ梗塞が脳のより中心部に存在する患者には症侯性脳梗塞が将来出現する可能性を考えて抗血小板療法を行なっています。それ以下の大きさで加齢変化よりラクナ梗塞の数が多く存在しいる患者には上記の危険因子の予防療法をお勧めしています
認知症(痴呆症)の原因には前述の様に全身性及び代謝性疾患の他中枢神経が原因としてはアルツハイマー型痴呆症、前頭側頭葉型痴呆症(ピック病等)、脳血管性痴呆症、水頭症、慢性硬膜下血腫等が代表的な疾患としてあげられます。この中で外科治療を必要とし更に認知症が治る可能性がある代表的な疾患に下記の水頭症と慢性硬膜下血腫があります。
水頭症とは脳内に本来150cc程度ある脳脊髄液が、さまざまな原因(出血、感染症、加齢等)で増量し脳を圧迫する事で脳血流が低下し認知障害が引き起こされる病態です。手術は余分な髄液をお腹の中に誘導する為の短絡チューブを設け、髄液がある一定以上の量(圧)になると流れ出る特殊なシステムを使用して脳の圧迫を解除させて治療をします。治療すると早い例では数日から1ヶ月程度の間に認知症が改善します。
慢性硬膜下血腫は多くの場合、頭部外傷後約1~3ヵ月経過して頭蓋内の硬膜下に血腫が貯瘤して脳を圧迫する事で症状が出現します。血腫の形成は頭部外傷時にCTやMRIでは描出が出来ない程度の小さな出血が存在し、この血腫の回りに膜が形成がされ、更にこの膜表面に新たな血管新生とそこからの出血が内部に起こる事で血腫が増量すると考えられています。一般的に推定血腫量が約50cc以上になれば手術適応があります。治療は頭蓋骨に長径1cm以下の小さな穴を設け血腫膜の内部を生理食塩水で洗浄する事で完了します。水頭症同様数日から1ヶ月程度の間に認知症が改善します。
MRIで認められる血管の瘤(こぶ)を脳動脈瘤と呼びます。まだ破裂をしてないものを未破裂脳動脈瘤と呼びます。色々な統計から全人口の約5%すなわち日本人全体で500万人の方が未破裂脳動脈瘤を持っておられる計算になります。従ってこの疾患は決して珍しいものではありません。また、脳動脈瘤は通常急に出来るものではなく数年間の間に出来たり或いは先天的に脳動脈瘤をもっておられる方のいるようです。動脈瘤の破裂率や自然歴についてはまだ充分に解明されてない部分もありますが、一般的に動脈瘤の大きさが5~7mm大以上の場合1年間に約0.5%の方(200人に一人)が破裂すると考えられています。この数が決して多い数字ではありません。ですからたとえ脳動脈瘤が見つかっても直ちに破裂を防止する治療法を考えるのではなく、この病気の状態や治療方法をじっくり医師に相談をされ今後の治療法や予防法を考える事が重要です。
しかし動脈瘤が一旦破裂した場合、例え破裂後に手術が成功しても3人に1人の方しか社会復帰出来ないと言われています。残りの2人の方は重い後遺症がのこるか最悪死亡される事もありえます。
この疾患はお薬で治療はできません。従って治療法は手術になります。現在行なわれてる手術法はクリッピング法とカテーテルを使用するコイル法の2通りの方法があります。クリッピング法は従来より行なわれてる方法で全身麻酔下に頭蓋骨を開けて脳と骨の隙間から動脈瘤に接近して動脈瘤の根元に丁度洗濯場バサミの小さい様な形のクリップで根元を遮断する方法です。またコイル法は足の根元の股動脈からカテーテルを挿入して血管の中から動脈瘤に接近する方法で動脈瘤の内部にコイルを充填する事で破裂を防止する事が出来ます。この方法はコイルの成分の問題からまだ充分に確立した方法ではありませんが、患者さんの肉体的な負担度からその適応が拡がりつつあります。どちらの方法も長所及び短所がありますので主治医の話をじっくり聞かれ判断される事が大切です。
最後に破裂率を下げる基本的な方法はありませんが血圧が高くなったり喫煙をすると動脈瘤が拡大したり破裂したりする危険性が高くなりますので、経過観察の場合は血圧の治療と禁煙が重要となります。